
KEIGAMA
TOKONAME, AICHI

知多半島の中央に位置し、穏やかな海風が心地よく吹き抜ける街、常滑。やきもの作りの起源を辿ると平安末期にまで遡り、日本遺産六古窯のひとつでもあります。
かつては、日本最大のやきもの生産地で、海運によって甕や壺、すり鉢などの生活用品が日本全国に運ばれていきました。インフラ整備とともに土管や電欄干といった大型なやきものや、タイルなどの建材、衛生陶器も生産されるようになります。また、江戸時代末期には急須の生産がはじまり、現在も職人達が作り続けています。
何百万年前、東海湖の底に堆積した土と、太陽、風、水、火が合わさり、様々なやきものを作り続けてきたこの地で、千年の歴史の延長線上に佳窯の仕事があります。
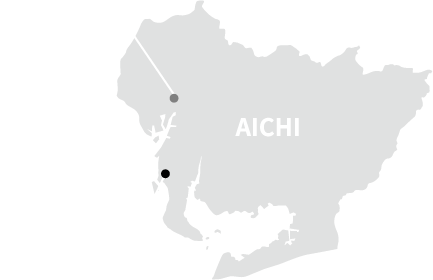
祖父の代に盆栽鉢の製造で創業し、宮内庁をはじめ国内外に大物の盆栽鉢をおさめてきました。その当時、常滑は大型のやきものが得意な産地だったので、どの窯元もとても大きな石膏型があり、扱う土の量も現在と比べ物にならないスケール感でした。成形は1階で行い、乾燥させるために2階へ運んでいたため、持ち上げやすいように天井が低い窯元が多いのも特徴です。
時代を経て食器へ移行していき、3代目の現在は、先代から受け継いだ技術をもとに、食器やインテリア用品など幅広く手掛けています。


先々代・先代から受け継いだ、たたらの技術をベースとし、形状によってロクロを使った制作もしています。すべての工程に人の手が入ることで、細やかな表現やひと手間をかけることができるため、手作りにこだわってひとつひとつ制作しています。小回りのきくメーカーとして、サイズや色などお客様のご要望に丁寧にお応えしています。
また、常滑には特有の原料や技法が数多くあります。それらの可能性を探究し最大限に活かし、土地の個性が伝わる商品を作り続けていきます。

2000年代に発足した、常滑焼の可能性を探る”盤プロジェクト”がbanシリーズのはじまりです。
常滑の窯元、急須職人、作家がそれぞれの技術を持ち寄り、受け継がれてきた伝統を次代に繋げたいという思いによって、約10年にもわたる開発を経てbanは誕生しました。
脈々と続く作り手の思いと、海に面しゆっくりとした時間が流れる、おおらかな土地の特質が、器に映り込んでいます。
風土をまとったbanは、ただシンプルに土と向き合い、料理が最大限に引き立つよう、余白を大切に、すべて手で仕上げています。




banシリーズ以外にも、ご要望に応じてオーダーを承っております。お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
公式オンラインストア工房には、ギャラリーを併設しており、各種サンプルもございます。
ご来訪の予定をお知らせいただければ、ご覧いただけます。
*ご来訪の際は、メールまたはインスタグラムDMよりお問い合わせください。
©️Copyright 2025- 有限会社マルヨ久田製陶所 All Rights Reserved